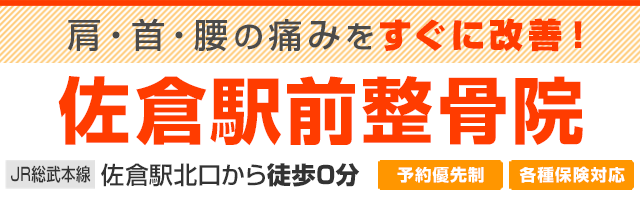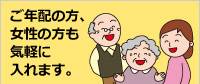肉離れ


こんなお悩みはありませんか?

強い痛み
→筋肉が部分的に断裂している状態のため、強い痛みを伴うことが多いです。
内出血
→断裂によって傷がつくと内出血が起こり、皮膚の変色や腫脹が起こります。
皮膚がへこむ
→断裂部分の変形がへこみとして外見でわかる場合もあります。
コンパートメント症候群
→肉離れによる腫れが大きくなると、コンパートメント症候群という症状がみられることがあります。負傷部分の内圧が高まり、血管や神経を圧迫することでしびれ等が起こり、重症の場合筋肉が壊死することもあります。
瘢痕組織、血腫
→瘢痕組織という通常の筋肉よりも硬くしこりのような部分や、血腫という血の塊が残る場合もあります。
肉離れで知っておくべきこと

肉離れは、基本的にスポーツや運動中に起きることがほとんどです。筋肉が収縮する動きに対して、同じタイミングで引き伸ばされるような力が加わると、筋肉に過剰な力がかかり発症します。特に下半身の筋肉に起きやすく、太ももやふくらはぎでよく見られます。
筋繊維自体が切れると筋断裂という状態になり、自力で動かすことが困難になり、強い痛みが生じます。部分的な断裂のほか、完全に断裂してしまうこともあります。
完全に断裂した場合、回復には長い時間が必要となることがあります。筋肉が修復した後も瘢痕が残る場合があり、筋肉が突っ張る感覚や運動時に軽い痛みが出ることもあります。
症状の現れ方は?

肉離れは運動中に発症することがほとんどで、特に下半身の筋肉に多く見られます。
筋肉が収縮する際に、逆方向に引き伸ばされるような力が加わると筋肉に過剰な負担がかかり、部分的な断裂が起こります。ジャンプやダッシュ、着地など、瞬間的に大きな力がかかるタイミングや柔軟性の低下、準備運動不足なども原因の一つとなります。
症状の度合いにもよりますが、痛みが強いのが特徴で、負傷後は動かすことが困難になる可能性が高いです。時間が経過すると、内出血や腫脹、熱感などの炎症症状が遅れて現れることがあります。損傷の度合いによってⅠ度、Ⅱ度、Ⅲ度に分類され、Ⅲ度まで進行すると、筋肉が完全に断裂している状態になります。
その他の原因は?

肉離れは基本的に運動中に発症することがほとんどで、日常生活の中では急に力を入れたときや踏ん張ったとき、転んだときに起きることがありますが、スポーツ時に発症する確率に比べると、めったに起きないと言ってもよいでしょう。
肉離れの原因は、収縮する力に反対の力が加わることで過剰な負荷がかかり、筋肉が損傷することです。その他にも、筋肉や腱自体の柔軟性が低下していたり、筋力が落ちた状態から急に激しい運動をすると、肉離れが発生することがあります。そのため、運動前にはストレッチや準備運動を行うことで、肉離れを予防しやすくなります。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れの施術では基本的に保存療法が選択されることが多いです。筋肉の損傷のため、無理に動かさずに修復されるのを待ちますが、痛みが引き状態が良くなっても筋肉の硬さや瘢痕組織の部分が残ると再発しやすくなります。
瘢痕組織とは、傷ついた筋肉を修復する過程でできる組織で、イメージとしては切り傷や火傷の傷跡のようなものです。この瘢痕組織が残ると、運動時に軽い痛みが残ったり、突っ張る感覚が残ることがあります。
短期間のうちに施術を受けることで瘢痕組織が残ることは少なくなりますが、逆に長時間放置してしまうと、症状が取りにくくなり、周りの筋肉に悪影響を及ぼす可能性もあります。
当院の施術方法について

当院でも基本的に保存療法とともに、電気を使った施術を行っています。
痛めた直後には、RICE(安静、冷却、圧迫、挙上)処置を行うことで状態の悪化を防ぎ、回復をスムーズに進めることができます。スポーツをする方は、ぜひ調べてみてください。
時間が経過した後は、硬さを残さないように筋肉をほぐしながら、組織の回復を進めていきます。この時に電気を使うことで、細胞の動きを活性化させ、傷の修復を早めるとともに、痛みの軽減が期待できます。
痛みが引いた後は、ストレッチや軽いトレーニングを行い、筋肉や腱の柔軟性を高めていきます。これにより、動きやすさを取り戻し、再発の防止にも注力していきます。
改善していく上でのポイント

肉離れを起こした直後は、施術方法にも記載したRICE処置を行ってください。受傷直後の対応で痛みや腫れを軽減し、回復をスムーズに進めることができますので、なるべく状態が悪化しないようにしましょう。
また、肉離れの場合、筋肉の損傷度の判別には画像診断が必要な場合もあるため、痛みで歩行が困難になる、または見た目でわかる変化がある場合には、医師の診断を受けることをお勧めします。
基本的に保存療法となるため、日常生活でもなるべく患部に負担をかけないようにし、スポーツや運動は避けるようにしましょう。痛みが引いた後も、筋肉の状態が完全によくなるわけではないので、リハビリやストレッチを行い、再発防止とともに後遺症が残らないようにしていくことが大切です。
監修

佐倉駅前整骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:沖縄県読谷村
趣味・特技:筋トレ、読書